作家の小説に一時期はまっていて、著者名に「Jr」がついているころから、ずっと追いかけていた。その当時、翻訳されていたものは全部読んでいたのではないかな。どうやって知ったのかというと、たぶん大江健三郎のエッセイで。「坑内カナリア理論」で知ったはず。炭鉱ではガスの流出と爆発が危険であるが、人間の感覚器では異常を感知できない。そこでカナリアを坑内に入れると、最初にカナリアが卒倒する。そこで坑夫は退避し被害を少なくすることができる。作家も坑内に持ち込まれたカナリアと同じで、世界や社会の危機をいち早く感じ取り、さまざまなパフォーマンス(特に小説によって)で警報を鳴らすのが使命なのであるという考え方。これはそのとおりだと思う。自分が小説を読む方法でも、ヴォネガットと大江の考えを利用いていると思う。そんな具合に、自分にとって、この作家は社会的な危機をオブラートでくるみユーモアを交えて語る20世紀のユマニストである。ただ、多くの読者には、奇想天外で能天気なほら話をする陽気なおじさんということで通っているみたい。仕方ないと思う年一方で、残念だと思う。
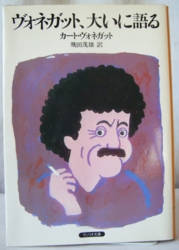
このエッセー集は1960-70年代前半にかけての講演やエッセイ、インタビューを収録したもの。同じような体裁の本に「パーム・サンデー」(早川書房)がある(こちらはいち早く手放したので中身を覚えていない)。サンリオSF文庫なので、入手困難かとおもっていたが、KINDLE版が出ている。よかった。主要長編もKINDLE版が出ている。よかった。
最重要なのは「自己変革は可能か」というプレイボーイ・インタビュー。
この人は世界と社会にとてもペシミスティックな想念をもっている。これまで人間は愚かな行為をさまざま働いていて、その失敗を反省しないし、改善していない。そういう例には、1944年のドレスデン爆撃(歩兵としてノルマンディ上陸作戦に参加した作家は捕虜になり、ドレスデンの収容所にいた。その爆撃で10万人ともいわれる死傷者がでた)。あるいは進行中の案件としてヴェトナム戦争とビアフラの内戦がある。特に後者はアメリカとソ連が無関心だったので、被害は拡大する一方であった。それに、1970年代には現代に通じる宇宙論がまとまったころで、数十億年後に太陽が爆発して地球は消滅し、さらに熱死によって宇宙の運動がとまってしまう(宇宙の膨張は止まることがなく、2兆年後には観測できる宇宙には銀河系しかないということを作家が知ったらどういうおもいになっただろう)。そういう悲惨や悲嘆があり、これからもそれにつきあわなくてはならない。涙もでてこないほどの絶望と孤独。これが作家のいる場所。そのような悲嘆と悲惨の場所で、人の取るやり方には2種類あり、ことさら悲しみを嘆く人と、あえて笑いを演出する人。作家は後者。このエッセイ集に収録された講演は翻訳のためか、笑えなくてむしろ生真面目さが目につくのだが、きっと聴衆、中でも若い人たちは笑い転げていただろう。笑いがあるから、あるいは笑う行為によって、人は慰められる。慰められた顔のために、作家は一生懸命、ほら話をする。そして、読者や聴衆はもっと笑う。悲惨や悲嘆に抗するための笑い。
作家は坑内カナリア理論の実践と考えているのか、いろいろなドキュメンタリーを書いている。内戦時のビアフラ訪問とか、アポロ17号の発射とか、猟奇連続殺人のレポートとか(カポーティ「冷血」に影響されたな)、ブラヴァツキー夫人の評伝とか、ヴェトナム戦争への科学者加担とか。ここで作家は「別の惑星からの訪問者」と自らを規定する。現世のしがらみや利害の関係から切り離された第三者の視線を持つことだ。それはアダム・スミスの「利害関係ない第三者」が善悪を判定できる、ないし基準になるという考えに似ている。というか18世紀のスミスを20世紀のよみがえらせるときの優れた言いかえだ。そのような第三者の視点からみると、他人への暴力・強制された死は理由のいかんを問わず痛ましく、反道徳的で、人間の愚傘を現したものだ。そこで、再び作家は悲嘆にくれ、ほら話をすることになる。
このような悲惨と悲嘆の連鎖から解放されるために彼は「拡大家族」を構想する。昔の大家族にあったように、同じ姓を持つ人々は助け合いましょう、なにより苦しみや悩みを語り合い、心理的な浄化を目指しましょう(社会的なセイフティネットになることも期待している)。この構想は「スラプスティック」(ハヤカワ文庫)に書かれたね。自分は若かったせいか、当時はあんまり感心しなかった(そのころの自分にとってのベスト3は「プレーヤー・ピアノ」「母なる夜」「スローターハウス5」。社会的な主題を持つシリアス作品ばかり)。こういう拡大家族の嗜好は同時代の作家フィリップ・K・ディックにもあって、「ヴァリス」「暗闇のスキャナー」などがそれ。ただディックの拡大家族は悲しみと孤独を再生産する仕組みになってしまう。ヴォネガットと同じように世界や社会への違和感や悲しみを持つところから出発しながら、二人の行き先はずいぶんと異なってしまった。その理由を考えると、いろいろ書けそうだが、ヴォネガットの本の感想にあわないのでここまで。
この作家の小説は当たり外れが大きくて、「ガラパゴスの箱舟」1985年はよかったけど、次作の「青ひげ」1987年があわず、そこで追いかけるのをやめた。