これまでにクイーン「Yの悲劇」は、鮎川信夫訳(創元推理文庫)、大久保康雄訳(新潮文庫)、田村隆一訳(角川文庫旧版)で読んできた。ほかに井上良夫訳、宇野利泰訳、鎌田三平訳、越前敏弥訳と複数の翻訳がある。さて、ここに今は入手難になった平井呈一訳がある。この国に西洋怪談を紹介した第一人者であり、永井荷風の弟子であり、江戸文学のオーソリティであって、なにより奇人であった。詳しい人物像は、荒俣宏「稀書自慢、紙の極楽」(中央公論社)を参照してください。
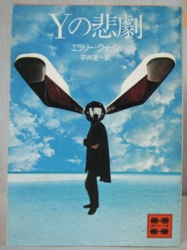
この人は探偵小説の翻訳家でもあり、たとえばヴァン・ダイン「僧正殺人事件」、カー「黒死荘殺人事件」(このふたつはなつかしい)、セシル「ペテン師まかり通る」(これはみたことがない)があり、クイーン「Yの悲劇」もある。以前「僧正殺人事件」を読んだ時の感想に、「その人(平井呈一)が訳したこの小説は、すこし風変わりなところがある。ファイロ・ヴァンスはアッパークラスのニューヨーカーなのだが、なんと江戸弁でしゃべってしまう。もちろんふだんは意識的にきちんとした言葉使いなのだが、ときどき情に流れるときには地の言葉が出てしまう。それはマーカムやヒースも同じで、どうもニューヨークの真ん中で起こる事件とは思えず、むしろ神田下町あたりの商人屋敷で起きた事件のように思えるのだ。そういう趣向も面白いだろう。」と書いたが、「Yの悲劇」でも同じ。手元の田村隆一訳と比べてみようか。
まず、ドルリー・レーン登場時のセリフ。
田村隆一訳P48「これは、警部さん!」レーンはさもうれしそうに声をはずませた、「まったく意外というものだ。よくおいでになってくださった!」彼は大鉄を投げすてると、警部の手をにぎりしめた。「だが、私のいるところがよくわかりましたな、たいがいの人は、私を探し出すのに、ハムレット荘を何時間もさ迷いあるくところなのですがね」
平井呈一訳P53「いよう、これはこれは」とレインはさもうれしそうな大きな声で、「こりゃあ思いがけない。よくおいでなすった」と重い木鋏をそこへ投げ捨てて、サムの手を握った。「よくここにいることがおわかりでしたね。たいていの人は、ハムレット荘へくると、主人を探すのに何時間も、うろつくもんだがね。」
長女バーバラと話をするところ。
田村隆一訳P110「いや、おそれいりました」とレーンがほほえみながら言った、「しかしですね、私がこんなことを言いだしたのは、なにも古典の知識をひけらかしたいがためではないのですよ、警部さん……ええと、どこまで言いかけましたかな、お嬢さん、そうだ、これまでに、サイエンシアがユータピの足もとにすわったことがありましたかね?」
平井呈一訳P122「ははは、ちげえねえ」とレインはにっこり笑いながら「だけど、こりゃなにも、小生の古学の知識をひけらかしているわけじゃないんだぜ、警部。……つまりね、ミス・ハッタ―、あたしの、伺いたいのは、シェンチアがユータピの足元にぬかずいたことがあったか?という……」
捜査に失敗して手を引くところ。
田村隆一訳P386「いや、やっぱり手をひきます」とレーンはきっぱりと言った、「どうしてもやめますよ、警部さん」老優は椅子から立ちあがると、食卓のそばで身をこわばらせた。「もはや私には、事件に介入する権利はありません、ジャッキーが死んだ以上……」彼はかさかさの唇を舌でしめした、「いや、はじめから、警察のお手伝いをすべきではありませんでした。どうか、私を解放してください」
平井呈一訳P417「いや、やめます」とレインはあっさりいった。「あたしは手を引きます、警部」といって立ち上がると、テーブルのそばで棒のように立った。「あたしには、今となったらもう手出しをする権利はない。少年の死は……」と乾いたくちびるをしめして、「いや、とにかく、最初からあたしはお手伝いなどしなけりゃよかった。どうか、このまま手を引かしてください。」
ドルリー・レーンは元シェイクスピア俳優であるのだが(その職業で巨大な邸宅を構えるほどの資産を稼ぎ、60歳を前に引退したというのが、21世紀には驚きになるかもしれない)、平井呈一訳でみると西洋のスノッブないし文化貴族の面影はない。俳諧か茶道の師匠が引退して、路地裏の一軒家で趣味にふけっているような面持ちになる。なるほど、西洋の文化貴族は訳者からすると江戸の風流文化人に見えたのだろう。そのような人物にしたおかげで、ニューヨークという当時最先端の都市にある化け物屋敷の怪異というのが、「神田下町あたりの商人屋敷で起きた」人情譚になってしまう。それが「翻訳」という仕事に妥当なものであるかどうか、素人である自分には、さあよくわからない。一般向けではないが、珍重できますというところまで。レーンほかの登場人物の会話を、にやにやしながら読めたので。黒岩涙香の翻案ものを読んでいるような気分になった。
(とはいえ、この5年間に3回目の読み直しとなると、気力が続かず、途中でやめました。)
2016/11/16 エラリー・クイーン「Yの悲劇」(講談社文庫)-2 1932年 に続く。
エラリー・クイーン「ローマ帽子の謎」→ https://amzn.to/43T90fY https://amzn.to/43QwpOZ https://amzn.to/3TN2piB https://amzn.to/4aHlE3M
エラリー・クイーン「フランス白粉の謎」→ https://amzn.to/3U8X5at https://amzn.to/3TPkMDq https://amzn.to/3VQxKUf https://amzn.to/3xugUQQ
エラリー・クイーン「オランダ靴の謎」→ https://amzn.to/3TNV6Hn https://amzn.to/4aMS3pw https://amzn.to/49ofEMk https://amzn.to/3JeorG5
エラリー・クイーン「エジプト十字架の秘密」→ https://amzn.to/3TIK9Xy https://amzn.to/3Ub9SZ5 https://amzn.to/3vJZcYX https://amzn.to/4cLJi0X
エラリー・クイーン「ギリシャ棺の秘密」→ https://amzn.to/43PGonM https://amzn.to/43SqWHB https://amzn.to/3xr7G7U https://amzn.to/4cQvQZO
エラリー・クイーン「Xの悲劇」→ https://amzn.to/3PQUEqH https://amzn.to/3vMnqSu https://amzn.to/4aNMF5C https://amzn.to/4aOWbFx
エラリー・クイーン「Yの悲劇」→ https://amzn.to/3PV19sv https://amzn.to/49zoy9Q https://amzn.to/4aoaSjp https://amzn.to/3vJIitw https://amzn.to/3Ja6jwP(平井呈一訳)
エラリー・クイーン「アメリカ銃の謎」→ https://amzn.to/3vLr66Y https://amzn.to/4aN0VMc https://amzn.to/3xugAl6 https://amzn.to/3vBZyRA
エラリー・クイーン「Zの悲劇」→ https://amzn.to/43RmGIk https://amzn.to/4ap0NT3 https://amzn.to/3TNVkOJ
エラリー・クイーン「ドルリー・レーン最後の事件」→ https://amzn.to/49wsIzp https://amzn.to/43Py6fK https://amzn.to/49wsZlV https://amzn.to/49tw7Pi
エラリー・クイーン「シャム双生児の謎」→ https://amzn.to/3PUbQvf https://amzn.to/43OehW9 https://amzn.to/3TTSRCi
エラリー・クイーン「チャイナ・オレンジの謎」→ https://amzn.to/49rrp4B https://amzn.to/3PUtgYI
エラリー・クイーン「エラリー・クイーンの冒険」→ https://amzn.to/3xxBLms
エラリー・クイーン「スペイン岬の謎」→ https://amzn.to/49wJVZr https://amzn.to/3UadICH https://amzn.to/3J9rTSn
エラリー・クイーン「途中の家」→ https://amzn.to/3PQULT9 https://amzn.to/3PW1R8L
エラリー・クイーン「日本庭園殺人事件」→ https://amzn.to/3TS8zxP https://amzn.to/3xqj7fX
エラリー・クイーン「悪魔の報酬」→ https://amzn.to/4aPg2ET
エラリー・クイーン「ハートの4」→ https://amzn.to/4aJiDQw
エラリー・クイーン「ドラゴンの歯」→ https://amzn.to/3TYIdui https://amzn.to/3vMClfn
エラリー・クイーン「神の灯」→ https://amzn.to/3xugIB6
エラリー・クイーン「大富豪殺人事件」→ https://amzn.to/3xBuO3r
エラリー・クイーン「エラリー・クイーンの新冒険」→ https://amzn.to/3U8WpSq
エラリー・クイーン「災厄の町」→ https://amzn.to/49sunpG https://amzn.to/4aD63lU https://amzn.to/3JvSCsB
エラリー・クイーン「靴に棲む老婆」→ https://amzn.to/3xu6lx6 https://amzn.to/3TSaKkR
エラリー・クイーン「フォックス家の殺人」→ https://amzn.to/43OcPmB https://amzn.to/3Jgr1es
エラリー・クイーン「十日間の不思議」→ https://amzn.to/3TT2nWg https://amzn.to/4cOrdiG
エラリー・クイーン「九尾の猫」→ https://amzn.to/4cQ5xCT
エラリー・クイーン「ダブル・ダブル」→ https://amzn.to/4auBpeW https://amzn.to/3vIPPZG
エラリー・クイーン「悪の起源」→ https://amzn.to/3VS1aRM
エラリー・クイーン「帝王死す」→ https://amzn.to/3xB5BWS
エラリー・クイーン「犯罪カレンダー」→ https://amzn.to/3U7GkN2 https://amzn.to/4aMSAb0
エラリー・クイーン「緋文字」→ https://amzn.to/3JbwN17
エラリー・クイーン「ガラスの村」→ https://amzn.to/49yLl5A
エラリー・クイーン「クイーン警視自身の事件」→ https://amzn.to/43PyFGo
エラリー・クイーン「クイーン談話室」→ https://amzn.to/3Jclndy
エラリー・クイーン「最後の一撃」→ https://amzn.to/4cQw6YM
エラリー・クイーン「二百万ドルの死者」→ https://amzn.to/4aMSO1Q https://amzn.to/3J7HbXM
エラリー・クイーン「盤面の敵」→ https://amzn.to/3PWlFci
エラリー・クイーン「第八の日」→ https://amzn.to/3VMM3sV
エラリー・クイーン「クイーンのフルハウス」→ https://amzn.to/4aKXOEu
エラリー・クイーン「三角形の第四辺」→ https://amzn.to/3vBzk1B
エラリー・クイーン「顔」→ https://amzn.to/3J7GVIi
エラリー・クイーン「最後の女」→ https://amzn.to/4aLQhVJ https://amzn.to/4arej8S
エラリー・クイーン「心地よく秘密めいた場所」→ https://amzn.to/3xpZZ1L
