中学や高校の歴史の授業がつまらなかったせいか、古代史には興味を持たなかった。成人後は、せいぜいウィルヘルム・フルトヴェングラーの祖父やアガサ・クリスティの夫が考古学者であるとか、旧約聖書の時代が重なるとかそれくらい。知識として、ナポレオンのエジプト遠征からギリシャ・ローマ以外の古代史研究がさかんになり、シュリーマンのような素人から学者になった人がいるとか、ツタンカーメン王の発掘のあと「王の呪い」なるものがあったとか(後者はデバンキングされて、呪いのような事象がなかったことがわかっている)。そのくらい。
おおよそ紀元前8000年くらいからチグリス・ユーフラテス川流域とナイル川流域に最初の文明が生まれた。高校まででは、加えて農業生産の向上とか、鉄その他の金属加工技術の発展とか、アニミズムの地域宗教だったのが世界宗教になったとか、それくらいを応えられればOKだったのかな。とりあえず上記の河川の流域に、アシュメール・アッシリア・エジプト・ヒッタイト・フェニキア・ペルシャ・イスラエルなどの古代帝国が生まれ、長くて5000年、短いと500年くらいの隆盛ののちに滅びた、という理解にとどめる。これら1960年代に書かれた情報はすでに古くなり、細部や解釈はもっと新しい本を求めなければなるまい。
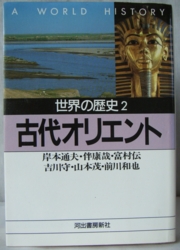
さて自分の興味に即して、気の付いたところ。
・たぶん村とか惣とかの家族や部族の共同体があったところに、「国」ができる。国ができたときには、すでにステート・ネーション・資本の機能が備わっている。すなわちステートの点では法の整備であり、それを運営する官僚機構がある。ネーションは部族ごとの宗教を統合した国民宗教を国家が管理し、人々に落とし込んでいる。資本では、灌漑設備、道路や水道などのライフライン、王宮・神殿などの巨大建築を行う。それらを運用するための官僚組織があり、税と賦役を徴収し、兵士を軍隊に編成する。このような「国家」がすでに完成したものとして、文明の初期に登場している。自分には「国家」は家族や部族の共同体から道徳・宗教・労働を疎外したものと見えるのだが、国家の疎外形態は順次成長発展したのではなく、いきなり完成形として生まれたらしいのがとても神秘(ミステリー)。
・最初の国家が生まれると、その国家に対応するために、家族や部族の共同体が変容して国家を形成したのではないか、という妄想を持つ。すなわち内部の人々の要求とか一般意思が集約されて国家になったというのではなくて、国家が隣にあるからここに国家をつくるという外の圧力への対抗で国家ができたのではないか。もともと内の人々、市民、人民などの一般意思などには基づいていないから、国家は内の人々、市民、人民などを抑圧するものとして機能するではないか。ここらの事情はこの国の明治維新でも同じではないかなあ。なので、ロックやルソーの国家の起源に関する考えは事実に即していないのではないかとも妄想。
・紀元前に生まれた文明や国家や王朝は例外なく、没落し滅亡している。自分の興味で気になるのは、鉄その他の金属加工技術。なるほど鉄は武器や農具として極めて有効で、生産性を劇的に上昇する。その代り、加工のために膨大なエネルギーを必要とする。当時利用できたエネルギーは、木材のみ。そのために上記の紀元前に生まれた文明は、周囲の森林を破壊しつくし、砂漠に変えてしまった。多少は残ったものも、15世紀までの収奪で無くなった(シリアのレバノン杉など)。その後、この地域からは巨大国家や最新文明が生まれていない。エネルギーとエコロジーを有効活用できないと文明の寿命は長くない。
2015/02/25 堀田善衛/司馬遼太郎/宮崎駿「時代の風音」(朝日文庫) 1992年
・もしも紀元0年で「世界史」をエジプトなどの視点で書くとすると、エジプトとアッシリアだけでほとんどの記述が終わり、中国の情報が加わるくらいだろう。それくらいに、ヨーロッパと北アメリカは文明化から取り残されていた。それは15世紀ころまで同様。人間の文明の歴史が1万年くらいだとすると、現在世界を席巻している西洋文明はわずか500年の歴史しかないという新参者。その代りこの文明の作った強力な資本主義は、それ以外の文明が今後生まれる可能性をほぼなくしている。
今西錦司「世界の歴史01 人類の誕生」(河出文庫)→ https://amzn.to/3x3KZX6
岸本通夫/伴康哉/富村伝「世界の歴史02 古代オリエント」(河出文庫)→ https://amzn.to/4aquG5a
貝塚茂樹「世界の歴史03 中国のあけぼの」(河出文庫)→ https://amzn.to/43Ayhv5
村田数之亮/衣笠茂「世界の歴史04 ギリシャ」(河出文庫)→ https://amzn.to/3VzGDkW
弓削達「世界の歴史05 ローマ帝国とキリスト教」(河出文庫)→ https://amzn.to/3IQ6s8C
佐藤圭四朗「世界の歴史06 古代インド」(河出文庫)→ https://amzn.to/3TBcOxJ
宮崎市定「世界の歴史07 大唐帝国」(河出文庫)→ https://amzn.to/43AUycw
前嶋信次「世界の歴史08 イスラム世界」(河出文庫)→ https://amzn.to/43wLiWC
鯖田豊之「世界の歴史09 ヨーロッパ中世」(河出文庫)→ https://amzn.to/3TRElfK
羽田明/間野栄二/山田信夫/小中仲男「世界の歴史10 西域」(河出文庫)→ https://amzn.to/3TzlwMR
愛宕松男「世界の歴史11 アジアの征服王朝」(河出文庫)→ https://amzn.to/3TB3c5Y
会田雄次「世界の歴史12 ルネサンス」(河出文庫)→ https://amzn.to/3TwRHN0
今井宏「世界の歴史13 絶対君主の時代」(河出文庫)→ https://amzn.to/4asVbqv
三田村泰助「世界の歴史14 明と清」(河出文庫)→ https://amzn.to/4a8mW8c
河野健二「世界の歴史15 フランス革命」(河出文庫)→ https://amzn.to/4aquMd2
岩間徹「世界の歴史16 ヨーロッパの栄光」(河出文庫)→ https://amzn.to/4anRCm9
今津晃「世界の歴史17 アメリカ大陸の明暗」(河出文庫)→ https://amzn.to/3TvKUDm
河部利夫「世界の歴史18 東南アジア」(河出文庫)→ https://amzn.to/43AkXHg
岩村忍 他「世界の歴史19 インドと中近東」(河出文庫)→ https://amzn.to/3TQaunH
市古宙二「世界の歴史20 中国の近代」(河出文庫)→ https://amzn.to/3TvNZDb
中山治一「世界の歴史21 帝国主義の開幕」(河出文庫)→ https://amzn.to/4a8mUgA
松田道雄「世界の歴史22 ロシアの革命」(河出文庫)→ https://amzn.to/3TROxEQ
上山春平/三宅正樹「世界の歴史23 第2次世界大戦」(河出文庫)→ https://amzn.to/3x73j1D
桑原武夫「世界の歴史24 戦後の世界」(河出文庫)→ https://amzn.to/4a5l3Jx