笠原潔「改訂版 西洋音楽の歴史」(放送大学教材)のように、音楽の歴史を表現の形式でみていくと、どうしてもJ.S.バッハ以降はドイツの作曲家に系譜をみることになってしまう。でも、バロック時代以降のヨーロッパでは音楽が作られ聞かれる中心地はイタリアとフランスだった。その事実が前掲書のような音楽の歴史の記述からはもれてしまう。なぜそうなるのか。イタリアとフランスではオペラが音楽の中心だったから。前掲書の感想を書いたときに、18世紀の古典派以降は各国史が必要とメモを書いた。それはオペラの歴史を記述することで達成できてしまう。そういう目論見で、本書を再読した。前回の感想は以下の通り。
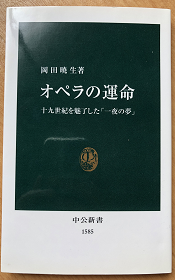
本書から簡単なオペラの歴史を箇条書きにしてみる。
・16世紀イタリア宮中で幕間劇インテルメディオという歌と踊りのレビューが上演される。直後に生まれたモンテヴェルディらのギリシャ演劇を復興したと称される音楽劇がオペラの先駆。
・17世紀の絶対王政時にバロック宮廷がオペラを上演する。昼食会から夜会まで延々と続く宮廷祝典の出し物のひとつで、王侯貴族のための機会音楽だった。中心はイタリア。以後、イタリア出身の作曲家や演奏家はヨーロッパ各地の王侯や歌劇場に就職して、オペラを広めた。各地の音楽の権威になった。
・18世紀の啓蒙君主時代はカストラートショー。メスタージオの台本に何人もが曲をつけた。このころからフランスオペラが隆盛。イタリアオペラの歌よりも詩文の朗唱に重きを置く。バレエと合唱が重視。グルックの「改革」は歌手のショーになっていたのと、フランス古典悲劇をモデルに筋と旋律をすっきりさせた。
・フランス革命で市民、大衆向けの祝典、軍隊行進が盛んにおこなわれ、救出オペラが流行った。ベートーヴェンやウェーバーなどに影響。
・ナポレオン没落後のウィーン会議(1814-15)以後の王政復古で、フランスではグランドオペラが流行る。見ればわかる筋と歌手の妙技、スペクタクルを楽しむ。
・19世紀半ばころからドイツ、イタリア、東欧などの非民主化国家で国民オペラが作られる(よその国で流行った国民オペラはイタリアやフランス様式。自国の民謡を使ったものは他国ではウケない)。フランスやイタリアでは異国オペラが流行(これもイタリアやフランスの様式で作られ、異国の旋律は色付け程度)。
・ドイツではワーグナーが君臨。王侯貴族の祝典や市民の社交だったオペラを芸術作品化し、静かに聴く鑑賞スタイルを作った。
・19世紀後半からの大衆社会になると、観客は王侯貴族やブルジョアの真似をするオペラを楽しまない。似たようなスペクタクルをテンポよく見せる映画に熱中する(無声時代はオーケストラの伴奏付きで、オペラやバレエと鑑賞の仕方は変わらない)。
・国民国家になると、金を喰い、国威発揚にはならないオペラを国家は支援しなくなる。政治的な利用目的がなくなり、オペラは自治体の文化施策によって補助金を出さないと成立しない(オペラを政治利用した最後がナチスドイツ)。
あと18世紀のオペラセリア(悲劇、正調)とオペラブッファの違いがおもしろかったのでメモ。
セリア: ギリシャやローマの古典を題材、カストラートやソプラノの高音域、荒唐無稽で予定調和的、華美な演出と装置、アリアを歌う歌唱力、決まり事に従うパターン化。典型例はヘンデル。
ブッファ: 〈現在〉のできごと、バリトンやバスの中低音域、キャラが劇中で変化するリアリズム、低コストな装置、重唱ができる演技力、変化にとんだ感情表現。典型例はペルゴレージ。
ギリシャ悲劇の復興(という勘違い)から始まったオペラがセリアのワンパターンになり、それにあきると〈人間〉を描くブッファに人気がでる。以後は市民や大衆の好みや政治状況などに影響されて、さまざまなスタイルが生まれていく。大衆化や国際化で生き延びようとしたが、1920年代の映画の革命によって命脈が途切れる。
でもオペラはある程度の観客を見込める文化産業で音楽産業。なので自治体はオペラ上演を支援するし、音楽祭の主催者もオペラを変えていく努力を継続する。WW2が終わってからはオペラの歴史は作曲家や作品を対象にするのではなく、産業や大衆化として語ることになった。観客も自国のディレッタントやスノッブから、観光客に代わる。
岡田暁生「西洋音楽史」(中公新書) → https://amzn.to/43DunDz
岡田暁生「オペラの運命」(中公新書) → https://amzn.to/3ZqYDz2