詐欺師フェーリクス・クルルの告白 ・・・ 2012年には光文社文庫で上下2巻の巨大な長編で翻訳されているが、1951年初版の新潮文庫では第1部と第2部(未定稿)だけが訳出されている。トーマス・マンは1875年6月6日生まれ、1955年8月12日没。ということなので、新潮文庫の初出の際には1937年アムステルダムで出版された途中までのものを使ったのだろう。その後、全体が出版されたのだろう。この小説ではフェーリクス・クルル18歳くらいまでしか書かれていない。この後光文社文庫の紹介を見ると、彼の晩年(そう、この小説はフェーリクス・クルルの自叙伝ということになっている)までのRise and Fall(栄光と没落)が書かれているようだ。古い版しかもっていないので、第2部までで感想を書いてみる。おかしなことだけどしかたがない。
年代がはっきりしないのだが、たぶん1880年ころにフェーリクスは生まれたのではないかしら。父は葡萄酒の製造販売を手がける実業家。まがいものをつめた三級酒を売っているので市場の評価は高くないが、彼は気にしないで新興成金の生活をしている(ヴィトゲンシュタインの祖父とかマーラーの父がモデルになっているのではないかという憶測をしたくなる)。あとは母と姉の四人家族。さて、フェーリクスは美貌の持ち主であり、神経質な子供として育つ。たぶん相当に頭はいい。しかし、この子供は、世の中のルールとか仕組みとかにまるで無頓着。といって、反抗心のある悪ガキではない。そんな反抗をして頭を殴られるのではなく、彼の選択は大人の真似をして彼らの信頼とか賞嘆を獲得しながら、一方で悪徳を働く(仮病で学校を休む、雑貨屋からお菓子を万引きする、など)。彼は罪の意識を持つことはない、なぜなら、彼はいつも仮面をかぶっていて、時と場合に応じてどのような人間にでもなることができるから。
おりからの不況で造酒屋は破産する。父が死に(自殺だが事故とされた)、姉は地方の小劇場の歌い手に就職し、母は下宿屋を開くことにする。さて、フェーリクスはパリのホテルに就職することが決まっているが、徴兵検査が終わっていないので出立できない。つかのまの平穏。そして徴兵検査での一世一代の演技。彼は癲癇発作の真似をし、まんまと医師の目をごまかした。
第2部最後の徴兵検査まで、会話はほとんどない。フェーリクスの独白のみが語られる。つまりはこの要領のよい悪漢が世界観を構築していく手順を描いているということなのだ。すなわち幼少期から思春期まで、彼は他者・他人を理解しようとしたり、その立場に身をおくことをしないし、できない。他者と無縁な独我論的な世界観を作っているのだ。そういう世界把握はたぶんだれにもあるけど、通常は他者、他人と交通することで挫折し、自分を世界にあわせなければならない。しかしフェーリクスは仮面をつけることで世界を手玉に取る。そのような方法はどこまで有効か。そこらへんがこのあとにかかれているのではないか、と。もしかしたらこの小説は独裁者の世界認識とか自己形成のモデル化であるかもしれないな。サルトル「一指導者の幼年時代」などを参考にしようか。こういう人物は探偵小説の犯人にたくさん出てくるね。フィルポッツ「赤毛のレドメイン家」、ヴァン=ダイン「僧正殺人事件」あたり。
あとこの小説には19世紀末への郷愁がある。解説によると、「ベニスに死す」は、この「詐欺師フェリークス・クルルの告白」に挿入される予定だったというからそれほど的外れでもないだろう。あの時代の中産市民階級の生活、風習などが丹念に書かれているので、なかなか進展しないストーリーにいらいらしないで、往時を偲ぶのがよし。横にクリムトなどのウィーン派の画集があるとよいね。
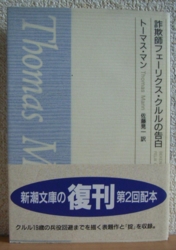
掟 ・・・ 1944年に書かれた短編。このころマンはアメリカにいて、ドイツ国民向けのラジオ放送に出演することがしばしばあった。解説によると、この短編の最終章も自身の声で朗読しドイツ向けに放送されたとのこと。
ストーリーは、出エジプト記の小説化。王の娘の私生児として生まれたモオゼ(ママ)。エジプトの奴隷であった部族の一員の余計物として育ち、エジプト人の官吏を殺して、メディアン人の下に逃げる。そこで目に見えない神ヤハウエを見出し(メディアン人の信奉する神だった)、これこそが唯一神であると確信した。そこでエジプトに戻り、布教を開始。当然、ほぼ全員が無視。ただ、モオゼは出生のためにファラオ(王)と交渉することができた。その失敗ののちの過酷な仕打ちのために部族の憤懣が募り、モオゼは指導者に選ばれていく。そしてエジプト脱出。いくつかの奇跡(紅海を二つに引き裂く、空からマナを降らせ食料とする)を合理的に説明し、砂漠を越えたのちにカアデシュという約束の土地を見つけ、先住の民と交戦して、これを略奪する。そして部族内のいさかいを裁き、道徳を教える。その厳格なルールは当然、民衆の反感を買い、しかも妻がいるにも関わらず黒人女と同棲していることが問題になる。そのときシナイ山が噴火。モオゼの守勢はここで反撃に出、神との対話のためにシナイ山にこもり、石版に掘った十戒を携えて戻る。聖書学の知見を取り入れて、近代人モオゼを記述する。
さて以下は個人的な読み方。すなわち、モオゼの偉大さの背後にある独裁者の誕生について。モオゼの行ったことを振り返ると、新しい神を伝えるには彼の言葉は貧しい(口が回らないことと、複数の言語を同時に使うので意味が通じない)ので、役割を分担するチームを作る。すなわち、兄アーロンの能弁、妹ミルヤムの予言術と太鼓による人心誘惑、モオゼの従兄弟で心酔者であるヨシュアと彼の組織する軍隊。彼らが激高するモオゼの言葉を部族一体に広め、定着する役割を果たす。さらに重要なのは、シナイ山に登ったとき、姿をみせないモオゼに落胆した民衆がアーロンとミルヤムに詰め寄って新しい神をよこせと要求する。そしてできた金の子牛の像のまわりで歌舞を始める。それをみたモオゼは激高して、子牛を破戒するとともに、この事態の首謀者と関係者をヨシュアの軍隊に命じて粛清する。そして石版に刻んだ十戒(モオゼはアルファベットを作ったことになっている)で、この共同体に法を布き、ライバル不在の状況で自身のみを権威とすることに成功する。ここにいたるまでのモオゼの、ときとして失敗や苦悩もあるやり口は、他の独裁者にも見られることであるだろう。
というわけで、次にみえてくるのは、モオゼと出エジプトの話というはるかに昔のことを語りながら、現在を批判するという迂遠で皮肉なやり方。民衆の煽動と、民衆の力を借りた自分の権威化をまずはナチスの指導者たちに重ねることができるだろう。そして、他の独裁者(スターリンにも、毛沢東にも)に重ねることができるだろう。そういう点ではオーウェル「動物農場」と同じ現代の寓話である。この文庫の編集者の意図もそのあたりにあって、この二つの小説をならべたのではないかなあ。あいにく、こちらは気軽に読んで笑えるものではないので、マンの意図が伝わるのは少数であるのだろう。こういう意図の本として、武田泰淳「司馬遷」(講談社文庫)があった。
トーマス・マン「短編集」→ https://amzn.to/3wo0cSB
トーマス・マン「ブッデンブローク家の人々」→ https://amzn.to/3wBU216 https://amzn.to/4bOGakw https://amzn.to/49LtbOq https://amzn.to/3wsimTk
トーマス・マン「トニオ・クレーゲル」→ https://amzn.to/4bQpSHY https://amzn.to/4bM1NSs https://amzn.to/49Fl3iy https://amzn.to/3uPArdm
トーマス・マン「ベニスに死す」→ https://amzn.to/3wofLtn https://amzn.to/49KJ2wR https://amzn.to/49HvGl2 https://amzn.to/42NwuCw
トーマス・マン「ゲーテとトルストイ」→ https://amzn.to/49ICOOa
トーマス・マン「魔の山」→ https://amzn.to/48nuF0h https://amzn.to/4bQ7UVG
https://amzn.to/49OwmVX https://amzn.to/4bKlMkv https://amzn.to/3SO9L4W
https://amzn.to/49LXWCW https://amzn.to/4bP7WNw
トーマス・マン「マリオと魔術師」→ https://amzn.to/3T9vMMX
トーマス・マン「リヒャルト・ワーグナーの苦悩と偉大」→ https://amzn.to/49HxmuM
トーマス・マン「ワイマルのロッテ」→ https://amzn.to/3OSHnxm
トーマス・マン「だまされた女」「すげかえられた首」→ https://amzn.to/3SNXCNk
トーマス・マン「ファウスト博士」→ https://amzn.to/3ORPhad
トーマス・マン「永遠なるゲーテ」→ https://amzn.to/4bK104r
トーマス・マン「詐欺師フェリークス・クルルの告白」→ https://amzn.to/4bObcc1 https://amzn.to/3SO9Nd4
シェーンベルクの未完のオペラ「モーゼとアロン」は、この小説の終結部と一致しているので(参照している本がおなじなのであたりまえ)、オペラの鑑賞者は読んでおくとよい。シェーンベルクは苦悩するモーゼ(バリトンのシュプレッヒシュテンメで不器用に語られる)と軽薄なアロン(リリック・テノールの流麗な歌)を対比している。激高する厳格なモオゼ、不倫にいそしむモオゼというのは、シェーンベルクのオペラにはいない。オペラは、ブーレーズ盤とケーゲル盤しか聞いたことがない。