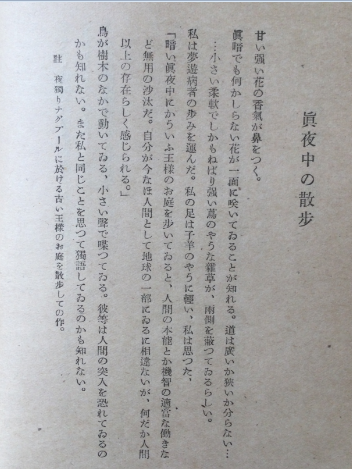
真夜中の散歩
甘い強い花の香気が鼻をつく。
真暗でも何かしらない花が一面に咲いていることが知れる。道は広いか狭いか分らない・・・小さい柔軟でしかも粘り強い鳶のような雑草が、両側を覆っているらしい。
私は夢遊病者の歩みを運んだ。私の足は子牛のように軽い、私は思った、
「暗い真夜中にこういう王様のお庭を歩いていると、人間の本能とか機知の適当な働きなど無用の沙汰だ。自分が今なほ人間として地球の一部にいるに相違ないが、何だか人間以上の存在らしく感じられる。」
鳥が樹木の中で動いている、小さい声で喋っている。彼らは人間の突入を恐れているのかもしれない。また私と同じことを思って独言しているのかも知れない。
註
夜独りナグプールに於ける古い王様のお庭を散歩しての作。
月夜
月が出る・・・
光線なるものよりもっと純なるもの、もっと柔いもので、樹木は包まれる。
ああ、何たる幻の存在だ。
一定の規則を知らずに繁茂した樹木は、路に迷ったもやもやの煙のように盛り重なって、有とも思われない風に灰色の唇を動かし、呪文の耳語を交わしている。
それは法悦の饒多に自らを幻化をしたものの姿だ。
それは魂を瓦解して、音楽のうちに溶け込んでゆく姿だ。庭の芝生に、感激の血を滴らした赤い花が咲いている。
花はしぼむことを知らない永劫の乙女だ。
音のように恋をささやく遍歴の武士がやってくるのを待っている乙女だ。
タヂ霊廟
風船玉から鳥を取り出した魔法師がいた。ああ、どういう魔法師がこの殿堂を生み出しただろうか。げにや、曙光の門だ。明朗たる光の洪水が波々と溢れる。
少年時代に、壮麗な太陽を受けた山脈の進軍がぱたと止まって、黙想の姿勢をとった夢を見た。不思議な方角から流れる音楽を耳にして目覚めたことがある。不合理と知りながら、完全に幸福に酔った瞬間を体験したことがある。これ等の刹那的記憶が、今一つの大きな表象となって、結晶し、私の限界一杯を満たして、一寸の余地だに許さない。
堂前に長方形の池がある。それを縁取る無数の糸杉は、光の面紗に包まれ煙っている。糸杉は池上に法悦の姿を投げて、私に地下にもう一つ、驚異の世界があると指示している。人若し私に、「君は虚偽の世界を見ている」とするならば、もとより私は彼を否定しない。虚偽と実在の区別は誰か知らんやだ。
殿堂の円天井をささえる円柱のかずかずは、平行線的に行儀よく垂直の釣合美を整えている。円天井を後ろから抱いている朝の空は、群青色に、一点の汚れさえない。私は今静寂な階段を上って、堂内に吸い込まれて行かんとしている。私は抵抗するに餘りに無力だ。私の体に触れる空気は温かく、香ばし、夢の平和は完成した。
それを破る一羽の鳥だもなし。
註
本作は前掲「女皇タヂ挽歌」前に書けるもの。
熱帯の海
熱帯の海は青畳のように平静だ。太陽の熱い光線に蒸されて、うとうと眠る・・・
船はその上を、夢路を分けて行くように滑る。
時に鯱や、鯨や、鱶が、小さい築山のような背中を波間に膨らませ、越後獅子の蜻蛉返りをうつことがある。もとより人間への示威活動でない、通る船人に見せる余興だ。
熱帯の海は平和だ。時に高く波打つことがあるが、大空の楽師に合せる管律の一波潤に過ぎない。
太陽は西に沈みゆく・・・扇形のように大きい黄金月がしづしづと東の空を登る・・・金襴の袈裟をつけた僧侶が、祈祷するため広い殿堂へ望む如しだ。
静寂に包まれた熱帯の海は、神聖な勤行の大広間だ。跪いて祈祷するのみだ。祈祷に言葉はいらない。神様と羅針盤を信ずればよい。
私共は運命を羅針盤と神様に委ねて、幽霊船のように船足の早い行進曲を奏でて行く・・・船は何ものも積んでいない。満載の貨物は冒険と夢の二つだ。
二等船客の一人が、甲板にハンモックを釣り、ながながと寝そべる。
人間の機嫌のいい時は、いつも小唄となる。彼は両手を頭の下に組み、足の片方をハンモックから甲板の上へ下し、ばたばたとそれを具合よく動かす。彼は低声小唄をで唸る。
「月の光に忍び来よ、
お話しすべき恋の一曲、
月の光に谷をわけ、
森の彼方に忍び来よ、
お話すべき恋の苦しみ。」
彼は上機嫌だな・・・油のような海を船で走る気持ちはまた格別だ。
彼はハンモックから立ち上がり、パイブに火をつける。パイプの火花は、静かな風に攫はれて油のように波に落ちる。
これは行手はるけき夢を追う至って呑気な冒険航海だ・・・こう海上を走ると、暗黒の胸に一つの涙といった寂しさはある。でも私はこの寂しい生活をどんなに望んだか知らない。
海上で感傷的にならない奴は人間でない。出来るだけ感傷気分に浸って見たい・・・感傷的になることは、ロマンチックになることなのだ。
しばらくすると、またもや二等船客の小唄が沈黙を破る・・・
「東を破るお日様は、
荒らくれ男に呉れてやれ、
月の光に、たれか知る、
甘き耳語あることを。」
私は甲板の暗い影を歩いている。鉄の手摺に凭れている、自分でないような感じを味わっている・・・
熱帯のうねうねした波に、船腹を舐めさせながら、古い習慣や、理屈を遠く離れて、身もし聞きもしないような未知の国へ帆走るぐらい、本当に喜ばしいことはない。
不思議な幻の世界が、すずしい声で私に呼びかける。行手の国に恋の花が咲いている、街の鳥が唄っている。
私は手摺に凭れながら海上を眺める・・・月光は黄金の波を洗う、水の音は風の音に交る。
だが私の心は月に洗われた波にない、月に答える風にもない・・・
「人間の運命」と言うことに集中されて。
マハラジャの呪文
マハラジャは絹の白衣をまとっている。浮彫式の模様が附いている。意味のわからない呪文が図案化されたものだ。
恐らくこの着物は、古い時代に千人も集まって、神様を礼賛しながら紡いだものであろう。
彼は部屋のなかを立ったり座ったりしている。部屋は彼とぴったり当嵌まっている。彼なくしてこの部屋は存在しないとさえ思われた。
彼は神龕に朝の祈祷を捧げている。すべての知識を支配する人間というよりは、むしろ謎を考えている子供に似ているといったような形。
「金と銀こそ尊けれ
これ宇宙を貫く血潮なればなり。
銅と鉄とを軽視する勿れ、
これ大地の動脈静脈なり。
神よ、われ金となり銀となり、
銅となり鉄となり、
すべての完全を誓うなり、
われ闇黒を恐れじ、死をも恐れじ。」
マハラジャは呪文を二度も三度も繰り返し、そしていった。
「私は真理探求の旅へと、世界の果まで行きます。私は力の限りを盡さなかったでしょうか。なぜ私は勝利を上げることが出来ないでしょうか。」
部屋の壁は薔薇色ダマスクの小型瓦張り、その感じの柔かで美麗なことよ。今日どんな動物園にも、その標本が見出されないであろう動物の毛皮が、床に幾枚も敷いてある。壁画は不思議な夢と地上の現実との組合せ、夢から見ると現実のためにその実際美を増し、現実から見ると夢のために感情を激動させている。純白直線の円柱と正方形桝形の天井を見るに、その一つ一つに違った絵が描いてある。
部屋の上段に小さい神龕が安置され、なかにスフィンクスが十字架にかかっている。部屋のすべてがつになって、この神龕に礼拝している。
マハラジャは部屋の中央、大きな机のそばに座っている。
机の四隅に、金と銀の蝋燭台が、二十六の枝をはって、その一つ一つに紅の小さい蝋燭が点っている。そしてまた机の中央に、それはそれは古い大きな瓶が置いてある。
彼は瓶のふたを開け、なかから古い枯葉を一つ取りだし、鼻の下へ持って行く・・・これぞ昔の女王様が先祖から給わったという薔薇の葉だ。
今幾千年の歳月が流れたが、薔薇はもとのままの香気を失わない。
彼がその葉を嗅いでいると、不思議な香気が部屋に満ちる。
部屋中が失心の喜びに喘ぐ。
註
本篇はマドラス滞在中、架空的に印度の王様を取り扱った作。
和蘭罌粟
沢山の和蘭罌粟が酸素提灯のように並んでいる、真赤な小さい提灯だ。
この花畑へ星の雨が数珠繋ぎになって降っている。大きな団扇の太陽は、まるで金紙を円く切ってぺたと張ったようだ。
諸君はこの光景を御覧になってこれは本当でないというかも知れない。普通の人は、こういう大きな太陽と、雨のように降る星の雨と、和蘭罌粟の畑を、一緒に眺めることが出来ないであろう。
でも私は今それを眺めている。
どうか諸君も、人生も恋も若かった昔にかえって考えて下さい。今日不可能だと笑って仕舞うようなことが、その頃は毎日起こらなかったでしょうか。
町を散歩して右へ行かずに左へ曲がったがために、諸君の一生に大きな変化を及ぼしたということはなかったでしょうか・・・諸君が将来の妻とするに至った美人に出会ったのではなかったでしょうか。
諸君は郊外を散歩して、生垣越しに偶然の歌を聞いた。春の花見に見知らぬ女とお話をした。その女がにっこり笑って、寂しく別れを告げた。こういうことが大きな事件となって、諸君を天井の雲の間へ登らしたことがなかったか。
不可能が可能になるような事件は、路傍にざらに落ちている。要は拾うか拾わないかにある。
現実派の数は夥しい、夏の蠅よりもっと多い。彼等は魔法を否定する。
しかし私は彼らにいう、
「和蘭罌粟の畑に雨がさんさんと降りそそぎ、大きな太陽がぬっと顔を出している・・・ああ、何と見事ではありませんか。」
ジムナ河を下る
逞しい船頭二人は黒白作り、見るからに空は緑一色の大理石、刻んだ驚くべき浮彫。
水は数千年の平和にはぐくまれ、大きい寛かな胸を膨らませて馥郁たる麝香を散らし、愛の一時を確認している。
頭を上げると烏の群れが天の護符をなってばらばら落ちる。私は自然の潤沢な饗宴に侍って、人生の概念を改める時だと思った。体を大事にすり寄せて微妙な振動を聞け、テントを畳んでこの心のなかに忍び込め! 燈火は燃えて遠くから響く人生の歌に音律を合せる。
私は今川岸を通り過ぎる。上手に一人の額を朱に染めた男がいる、神様の足元に座った大きな蝦蟇だ。
また他の一人が糸のようによれよれになった腰巻一つで、笛を吹いているを見る。誰が彼は笛の力で人生の神秘を解こうとするクリシュナでないと断定しよう。
恰も矢のように私を追って来る一艘の小舟がある。海賊船か、左うでない。乞食の船だ、だが神聖な乞食の船だ。船にいくつも印度教の仏像を乗せて、通行税取立てにやって来たのだ。
小さい人魚が五六十もいるかと見れば、彼等は私共の水へ投げた銅銭集めに水に潜る乞食の子供だ。さあ投げた、祈って投げろ、呪って投げろ、君等の自由だ。戻った所で一度水に触れると、どんなものでも浄化して荒神シバの御気に障らない。
もっと君等をびっくりさせるような事件がある。
二つの川の出会う所を見給え。裸体の軍隊が合掌の剣付き鉄砲で、もの凄い肉の城壁を築いている。
註
本篇はアラハバードに於いての作。ジムナ河の水上風景に拾った収穫、ジムナ河はアラハバードを流れる印度には珍しい綺麗な川で、この辺りの風景は八曲屏風に描きたいような題材になる。ジムナ河をしばらく下ると、川がガンジスと合流する所へ来る。ここが大変な場所で、無数の印度教徒が水の中に立って合掌したり呪文を唱えたりしている。罪業消滅の行をしているのである。
アラハバードは古代からの印度教の重要地で、玄奘三蔵の西遊記にも出ている。降って十二世紀の初頭、回教徒の大将ジャハブ・ウド・デイン・ゴーがこの地を征服し、十六世紀の半ばにアクバー王が城を作っている。英国がクライブの武力でアラハバードを領土にするに至ったのは、十八世紀半ばのことである。
恍惚境
彼は直接の世界を離れて間接の世界に入るように思う。彼は五色燦然たる世界から薄暮の世界に入るように思う。彼は銀鼠色の雰囲気で包んだ半透明の世界へ遠く巡礼の旅に出ているように思う。彼は人間生活を束縛する約束や道徳をあとに残して遥けき旅を歩いているように思う。彼に愛も友情も飛躍も躊躇も何物も無い。
彼は眠っているのでない、また目覚めてもいない。
彼は所謂半睡半眠の恍惚境を彷徨しているのであろう。それでも彼を飛びあがらせるほど驚かした瞬間があった。彼はその時体が何か電気にでも触れたように思った。彼は目を擦って周囲を見廻した・・・
眼前は闇黒である、然しこの闇黒が一色の欠乏からでなく、白よりもっと包合的なもの、いわば精神的な色である、一種の豊饒な色が五つも六つも化合して出来た不思議な色である。彼はこの不思議な闇黒を通じて何物かを見出そうとした。
彼は眼前の闇黒が音楽であるかのように思った。彼は実際にそれを聞くように思って、夜の甘い香ばしい雰囲気を味わっている。
彼は今茫漠として果てしのないあるような無いような世界の端に立っていると思った。彼はどうして此処へやって来たかを知らない、然しそれはどうでもいい問題であった。彼はこの時、遠い昔に小説か何かで読んだことのある言葉を思い出した。
「二つの世界に挟まった海の岸辺は長く続いている。ここで言葉に語られないような不思議な事件が起こった。」
彼はこの事件が何であっただろうかとしきりに考えた。すると彼は誰かが耳語するように思った。
「この不思議な事件は一人のお姫様に関係している。お姫様は独り海の岸辺にお住みになって、寂しさ無しに生きて居られないお方であった。」
彼はどこだか分からないが、二つの世界に挟まった海の岸辺を歩いているように思った。
夢のヒマラヤ登山
私はいつの間にやら森林地帯を離れた。
風は青くさい香気を散らして、麓の方から逆に上と吹き上がって来る。それが山の胸にまともに当たって、石や岩などがはね飛ばされ、ずっと下の谷底へ、がらがらと音をたてて転がり落ちてゆく。
前も後も分からない真暗闇だ。
私は心の安定を失って仕舞った。だが安定を求めようとさえしなければ自然にそれが自分にかえって来るようにも感じた。
私は云いおくれたが、今駕籠に乗って山を登っているのだが、駕籠が止まると、私は山の傾斜面をするすると滑って行くように、不思議な恐怖を覚えた。下の方を見てはいけないと思いながら、こわごわ見下すと、真黒な茫漠たる荒野が一面に広がっているらしく思われた。
この瞬間に私は、恐怖心を他へ紛らわそうとする意識が働くのだと感じた。
私は手を駕籠から外でさしのべた。私は何ものにも触れない。眼の下の闇黒が深い、私はそれを計ることが出来ない。
私は頭をあげて大きな空を眺めた、雲を排して金剛石のように光りだしたものがある、熱帯の星だ、三つ四つ。
八人の駕籠旲が、うんそらうんそらと重重しい足音を響かして、山の胸に真直な一文字を引いて登って行く・・・彼らは真暗闇でも物をはっきり見る猫だ、虎だ。
私は思った、
「運命の悪戯に出会って、永劫に空中にぶらさがり、私は動き通してなければならないとしたら、ああ、どうしようか。まるで神様がお蹴上げになった撚糸の鞠を、梯子団なしに取りに行くようなものだ。」
私はまた思った、
「一生に一度のことだ、狂人のような勇気を出して登って行け。凱歌を声高らかに唄って、前へ前へと突貫しろ、突貫しろ。」
私は頂上に近づくに従って、道が緩やかになるように感じた。しかし塹壕みたような所がここにもそこにもあって、そのなかから冷い風が吹き上がって来て、私の骨を噛むように覚えた。雪が永劫に解けないに相違ない。
八人の駕籠旲は軽るやかな足で、砂利を蹴って進んで行く。私は恐らく遠い昔、山が噴火でもした時吹きあげた溶岩の粉ででもあろうかと想像した。
私はもう山上の方を見たり、下の方を考えたりしてはいけないと決心した。地獄にあると聞いている忘却の谷のことを心に浮べた。
この瞬間に、大きな黄金の毬が、遠い海から吹きあがったと思った・・・月だ。私は月のように、立派に堂々と道のない天空が歩けると思った。
二つの酒
四角に作った広い池だ。
池には水蓮がいくつも咲いている。水の上を足の素敵に長い虫が歩いている。
水は青黒く瞑想の表象そのもの。太陽の光線を受けて、香港の街で売っている翡翠のように内部の魂を鈍獣な外皮の間から洩らしている。
池を取り巻く石造のベランダは、そのぼやっとした反射を受け、暗い陰影を深めている。ベランダの床は古い昔の模様瓦でしきつめてある。
ベランダの脇には、大きな正方形の部屋がいくつも続いている。人がそのなかに入ると顔が憔悴して真白になるそうだ、それは言葉を失って幻化するからである。
部屋の中央に、二つずつ、長方形の大きな石が置いてある。そしてその上に、古い昔の厚ぼったい織物がかけてある。織物は呪文模様で、月の光に照らされないと、その意味が明瞭にならないとされている。
このいくつもの石は、歴代の王様の墳墓である。
全身を白い綿布に包み、二つの大きな眼だけ出している回教徒の女は、さまざまの色で紡いだ花環を手へ持ち、忍び足して、王様の墳墓を覗いて歩く。
私は王様のいづれもの名前も知らず、歴史にも無関心であるが、ただこの部屋に溢れる陰鬱な空気のなかに、白い白い手が私を招くように感じて、回教徒の女に交って、王様の墳墓を覗いて歩く。
私はとある部屋の隅、大きな大理石の円柱にもたれながら、古びた本を読んでいる老人を見た。
彼は幾千年も幾萬年も、生きかわり死にかわって遂に得たと思われる平和な姿を持っている。彼は空虚な頭脳と疲労し切った肉体とからのみ得られる品位というものを備えている。
私は彼に尋ねた、
「何の本ですか。」
「神様の本です」と彼は答えた。
「生命の中に生命がある。生命の外にも生命を超越するもっと大きな生命がある。すべての生命の秘密を掌中に握っているのが、神様なのだ。人間は飽満な生活を夢み、美に憧れ真理を掴まんとして、神様の祭壇に跪く。神様の祭壇に、二つの瓶が置いてある。青春の霊酒と老衰の毒酒だ。人間は永劫の歓楽を望みながら、間違って、老衰の毒酒を飲みほしてしまう。しかし神様はただ微笑してその愚を取止めようとし給わない。神様は一向に無慈悲だ。それを非難する権利が人間にない。」
私は池に咲いている睡蓮を眺める。ベランダを静かに歩く。私は、青春の酒か老衰の酒かそのいずれかを手にしているかを惑い、また疑う。
註
本篇は印度高原の大都市ハイデラバッドにおいての作。題の場所はナイザム王代々の墓場であるが回教寺院になっている。門前に店がずらりとならんで神具を売ったり花環を売ったり線香を売ったりもしている。
ベンガル湾の声
私は印度を離れる数日前の一夜を、ベンガル湾のホテルで過ごした、
私は時に水底より響いて来る声を耳にした、
「起きてみな共、喇叭がわれ等を呼ぶ、開け開け!」
もう一つの声は私にこう言った、
「家畜の安逸を楽め。神の与える火に横たわって満足しろ、
剣や争闘は他に委ねて置け、自然の命ずる安眠に耽れ!」
血みどろに悶え這いまわる、
世界が嘗て見たことのない痛ましい光景から、
私の心は、その時、解放されて、
水辺の静寂をしばし楽しんだのである、
ああ、香ばしい夕べを迎える平和の嬉しさ!
私はその時叫んだ、
「二つの声よ、己が主張に苛立つな、
静かに、静かに、解決されない問題を出して私を苦しめるな、
私には私の問題がある、
それを今にも考えねばならない、
だが、今しばらくの静寂が欲しい。」
この時、私の部屋に花環が椅子にかけられ、
紅や白の花弁が床の上に落ちた、
二三匹の栗鼠が部屋の中を走り廻り、その花弁に触れた。
私は海に面するベランダに出て、頭を上げた・・・
銀の星が砂のように空に撒きちらされ、
椰子の木は葉の箒でそれを掃いた。
私は今日本へ帰って、この小さい書斎に座っている。
夕べが忍び足にやって来て、いつも私にベンガルの一夜を思い出させる、
だが私は、この時の声二つを払いのけることが出来ない。
註
詩中ベンガル湾のホテルとあるはワルテイアの一小旅館のこと。
野口米次郎定本詩集
第3巻
印度詩集
友文社
昭和二十二年五月十五日印刷 五月二十日発行 定価四十二苑