「資本論」の批判的な読みをしているからといっても、宇野弘蔵の「経済原論」を読む気にはなれなかったので、講演を基にし書き直した新書を選んだ。1969年初出。ながらく品切れだったのが2009年に復刊された。いくつか発見はあったものの、内容にはいささか失望。

1 『資本論』の経済学 ・・・ 資本主義を規制する三大経済法則があって、価値法則・人口法則・利潤率均等化の法則である。御大層な説明が続くが、経営学や企業会計では当たり前の話。資本は労働力を商品として購入している、利益は設備投資とあわせて労働者雇用に向けられる、個々の資本は利益最大化をめざすが企業間取引が行われるので利潤率の平均をとるで業界でほぼ同じになる。そういうことです。
マルクスは株式会社を例外的に扱っている(当時株式会社は少数)ので、分析がない(何しろ株式会社では資本と労働者の関係はあいまいになるのだ。なので搾取の構造を分析するのは難しそう)。マルクスの死後、レーニンやルクセンブルグ、カウツキー、ヒルファーディングらは帝国主義分析を行ったが、マルクスの理論をきちんととらえていないので不十分、なんだそう。
(ここはアーレントの議論を思い返すと別の不十分さがわかる。資本は未開拓の土地を求めて領土を超えて拡大するが、ネーション国家は領土に固執する。そこで帝国主義になると、ネーションの拡大と市場の拡大を同時に行うことになるのだが、上記のマルクス主義者経済学者はそこをとらえ損ねた。大きな理由は土台(経済)-上部構造(政治・法律)にとらわれすぎて、政治や国家の役割を軽視したことだろう。それに19世紀末からのグローバル化はマルクスの予言した階級分化に至らず、さまざまな階層を作ったし、社会も変えた。アーレントのモッブや大衆社会の分析のほうが帝国主義をとらえるには有効な見方だと思う。)
(通常、「資本論」の解説では生産資本だけが取り上げられるが、(たしか)「資本論」ではほとんど取り上げられない商人資本と金融資本も宇野弘蔵は分析する。そこから近代経済学までは近いし、さらに進めるとマルクス経済学もさまざまな経済現象を分析できるだろう。でもそれなら最初から近代経済学でやればよいよなあ。思考の節約になるし。)
2 マルクス経済学に特有な二つの用語「物神性」と「変態」とについて ・・・ 貨幣の物神性と資本の変態について。前者は商品-貨幣と貨幣-商品の交換過程は違うものだ。特に商品-貨幣では商品を所有する者を想定することが大事、という。これは商品を売る際に「命がけの跳躍」があるということだな。後者は、マルクスのG-W-G 'だと資本は拡大するだけにみえるが、実際は資本は構成を変化するという指摘。文章ではわかりにくいが、企業のバランスシートを見ればあきらか。またマルクスは商品交換は共同体と共同体の間で始まったと指摘していて、これも大事と宇野はいう。こういう指摘は、のちの人たちが継承した。たとえば、
柄谷行人「マルクス その可能性の中心」(講談社文庫)
柄谷行人「探求 I」(講談社)
岩井克人「貨幣論」(ちくま学芸文庫)
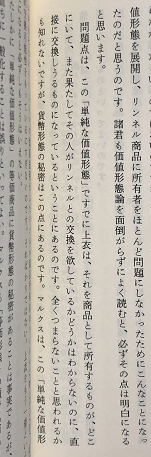
これらがあって、佐藤優は「柄谷行人は宇野弘蔵の系譜にある人」といったのだろう(「いま生きる『資本論』」新潮文庫)
3 理論と実践ー経済学と社会主義 ・・・ 毛沢東の「実践論」も持ち出して、理論研究の正当性を主張。
(この場合の実践はどうやら党派活動か組合運動あたりを指しているらしい。それもいいかもしれないけど、民主経営の企業をつくるとか、社会起業のNPOをするとか、地域通貨の実験をするとか、資本主義に抗する活動はもっとありうるのではないかしら。もっとも1920-30年代の不況期に行われたさまざまな実験はほとんど失敗するか、国家につぶされた。アーレントは人間の領域を私-公-社会の3つがあるとしたけど、マルクス主義者は社会ばかりを問題にする。レーニンのような革命家になろうとすると、私と公の領域から離脱することが求められるのだが、それは社会主義の可能性を狭めることになるのではないか。まあ、おれは根っからの自由主義なので、福祉国家になれば十分。社会主義は遠慮しますが。)
(マルクスは私や公のことも考えようとしていたが、マルクス主義は社会ばかりを問題にするのだが。このあたりのマルクスの若書きを十分に検討しなかったのだろうなあ。)
カール・マルクス「経済学・哲学草稿」(光文社古典文庫)-2
カール・マルクス/フリードリヒ・エンゲルス「ドイツ・イデオロギー旧訳」(岩波文庫)
宇野弘蔵は、マルクスの「資本論」からは革命の必然性は導かれないとする。本書には載っていないが、おそらく計画経済も肯定しないだろう。そうすると、宇野の考えはほとんどリベラリズムになる。橋本努「経済倫理 あなたは、なに主義?」(講談社選書メチエ)の指摘がそのまま当てはまる例でした。あと、宇野弘蔵は「資本家には資本家の仕事」があるといっている。これは労働者の「労働」と区別した言い方。それがアーレントの仕事、労働、活動の区分と重なるものかは不明。
マルクスが資本を研究する際にモデルにしたのは19世紀半ばのイギリス。当時の最先端の資本主義であったが、このあと資本主義は大きく変貌する。ひとつは株式会社などの経済内組織の複雑化や国家の市場への介入。もうひとつは資本が民族国家の領土を超えてしまうグローバル化。それに引きずられて領土拡大をもくろむ帝国主義。これらの古典的な資本主義の枠組みを超える事態が起きていた。マルクスの死後におきた現象に対してマルクスの理論を適合しようとする試みがあったが(ベルンシュタイン、ルクセンブルグ、ヒルファーディングなど)、党派や組合その他の運動の側はマルクスの理論に固執した。理論で説明できない現象が起きて理論が危機になり、乗り越えの可能性もあったが、その芽はついえた。本来なら1900-20年までにパラダイム転換されるべき旧パラダイムだったのが、党派的なイデオロギー装置に化して存続させられた、というわけだな(新パラダイムを作ったのはケインズ)。結局、マルクスの経済学は「革命の経済学」ではあったが(アーレント)、それ以上の説明をすることはできなかった。
以上、直前に読んだ川崎修「ハンナ・アレント」(講談社学術文庫)に引っ張られてしまった。上に参考エントリーであげた本も加えると、ここに書いてある内容はほぼカバーできる。そのうえ、わかりやすい。
本書は歴史的な意義はあるかもしれないが、もう読まなくてもよいでしょう。